吉村昭の紹介

吉村昭Akira Yoshimura
昭和2年(1927)~平成18年(2006)
東京府北豊島郡日暮里町大字谷中本(現荒川区東日暮里六丁目)生まれ。空襲で家が焼失するまでの18年間を荒川区で過ごす。学習院大学在学中に執筆活動を開始。昭和41年に「星への旅」で太宰治賞受賞。同年、「戦艦武蔵」を発表しベストセラーとなる。「死とはなにか、生とはなにか」を主題に、人間の本質を探究し、数多くの短篇と長篇を執筆した。妻は作家の津村節子。
好きなものあれこれ年譜
誕生(0歳)
東京府北豊島郡日暮里町大字谷中本(現東京都荒川区東日暮里6丁目)に、製綿工場を経営する父隆策、母きよじの8男として生まれる。2歳下の弟と一緒に遊ぶことが多く、周囲から「一卵性双生児」と呼ばれるほど強い絆で結ばれていた。卯年生まれのため、少年時代は兎を好ましく思っていた。また、家でアンゴラ兎を飼っており、兎の真似をして友人から拍手喝采を浴びたこともあった。

3歳ころの吉村と弟隆。
身延山で。
幼稚園時代(5歳〜)
日暮里町大字金杉(現東日暮里5丁目)の神愛幼稚園に入園。内気な性格だったが、忙しい母を気遣って一人で入園手続きを行うような一面も持ち合わせていた。幼稚園では、絵本を読んだり、紙飛行機を飛ばしたり、楽しく過ごした。カトリック系の幼稚園で、讃美歌の旋律の美しさに感動し、家に帰ってもしばしば歌っていた。

卒園式。中央・神父の左上が吉村。卒園記念には、生涯を通して大好きだった凧を欲しがった。
小学校時代(6歳〜)
東京市第四日暮里尋常小学校(現荒川区立ひぐらし小学校)に入学。成績優秀で6年間全甲だった。体格も平均より上で、休憩時間にとっていた相撲では強かったという。凧揚げに熱中し、学校から帰るとすぐに物干し台にあがって凧を揚げた。ベイゴマや夏には蜻蛉採りに夢中になった。少年雑誌や講談本などにも親しむ。放課後には辺りが暗くなるまでゴムボールで野球をしていたこともあった。
映画館通い
5歳の時、初めて活動写真(映画)を観る。歩いて行ける範囲に映画館が数館あり、6歳ころから親に内緒で週に2〜3回通った。製綿工場を営んでいた父から、商家の子供はお金の使い方を覚えなくてはいけないと、1日2銭の小遣いをもらっていた。邦画をはじめ、フランスやドイツ映画にも親しんだ。映画監督になるのが夢でシナリオを書いたこともあったが、肺結核を患い断念。
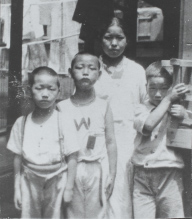
小学生のころ。友人と。右端が吉村。
中学校時代(13歳〜)
私立東京開成中学校(現開成中学校・高等学校)に入学。中学時代の特技は先生の声帯描写で、よく友人を笑わせていた。剣道部とボート部に所属。走高跳にも熱中し、158cmのバーを越えた時は天にも昇る心地であったという。
読書の楽しみ
中学2年の12月に肋膜炎にかかり、学校を2ヵ月休む。進級を心配した母が家庭教師をつけ、その人の影響で読書の楽しみを覚える。小説をはじめ、美術、考古学、天文学、科学者の伝記など、ジャンルは多岐にわたり、古本屋にもよく足をはこんだ。中学時で蔵書は2千冊に及んだ。
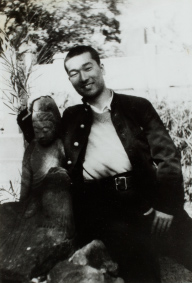
中学3年ころの吉村
寄席通い
ラジオで落語、講談、漫才を聴いていた吉村は寄席に興味を抱き、通い始める。学校帰りに上野駅の荷物預りに、制帽制服の上着、布鞄を預け、上野広小路の寄席「鈴本」に通った。友人を誘うこともあったが、一人で行くことが多かった。寄席通いは、大好きだった古今亭志ん生や可楽が亡くなるまで続いた。
東京空襲(18歳)
太平洋戦争が激化。吉村は空襲から蔵書を守ろうと、文庫本など約250冊を石油缶に詰めて庭に埋めた。4月13日の夜間空襲で家は焼失したが、本は無事だった。この年の12月、父がガンのため死去。前年には母もガンで亡くしている。
高等科時代(20歳〜)
旧制学習院高等科文科甲類に入学。松尾芭蕉の研究で名高い岩田九郎教授の俳文学を受講し、句会にも参加。句作を行うなど俳句に親しむ。翌年1月、中学2年で患った肺結核が悪化し、絶対安静の身となる。9月、左の肋骨5本を切除する胸郭成形術を受ける。療養中はラジオの放送劇に親しむ。楽しみとしていた読書は、長文の小説などは目の充血や痛みを伴うことから、俳句を読んだ。中でも、同じ肺結核を患って生涯を終えた尾崎放哉の句に強い共感を覚え、繰り返し読む。

高等科入学のころ
芝居見物
終戦後、芝居見物に熱中。主として歌舞伎、新派で、貧しかったため一幕見の席で観ることが多かった。観劇通いは7、8年続いたが、惚れぬいていた市村羽左衛門(15代目)、尾上菊五郎(6代目)、花柳章太郎、喜多村緑郎が亡くなると観に行くこともなくなった。
大学時代(23歳〜)
健康を回復し、4月、学習院大学文政学部に入学。文芸部に所属し、放送劇「或る幕切れ」を「学習院文芸」に発表する。出来上がった時は「嬉しくてならなかった」。演劇部にも所属していた。
津村節子との出会い
大学2年の時、後に妻となる北原(津村)節子が短期大学部から文芸部に入部。ともに活動を始める。このころ吉村は専ら短篇小説を読み、志賀直哉、森鴎外、川端康成、梶井基次郎の文章に魅せられ、外国文学にも親しむ。

文芸部の仲間と。前列右が吉村、その右上が津村。(昭和26年)
「学習院文芸」から「赤絵」へ
昭和26年10月、「学習院文芸」をガリ版刷りから活字印刷にするため、古典落語鑑賞会を開催する。文楽、可楽、柳好、円生、柳橋、そして大好きな志ん生を招き、その売上金で「赤絵」を創刊した。古典落語鑑賞会は以後4回実施。

古典落語鑑賞会の高座で。中央が岩田九郎教授、右隣が津村、その上が吉村。背後の金屏風は、学習院院長安倍能成が手配したもの。吉村は安倍に「絶大な畏敬の念」を抱いており、安倍のカントの著作に親しみ、哲学者を夢みていた。
結婚(26歳)
大学を中退し、三兄の紡績会社に入社(10月退職)。11月、節子と結婚。

結婚当時(吉村26歳、津村25歳)
同人誌時代
外国文学をしきりに読む。アメリカの作家、ヘミングウェイ、フォークナー、スタインベック、コールドウェルの短篇に感嘆し、繰り返し読む。また、フランスの作家、ピエール・ガスカールの短篇小説に強烈な衝撃を受け、愛読する。
ボクシング観戦
ヘミングウェイの「挙闘家」に触発された吉村は、自分でもボクサーを主人公にした小説を書いてみたいと思い、「鉄橋」を執筆。芥川賞候補になる。この小説を書くために、ボクシング関係者に会ったり、試合を見に行くことを続けているうちにボクシングの魅力にとりつかれる。試合会場だった後楽園ホールに、多い時で週に2回通っていた。ボクシング熱はその後7、8年続いた。
相撲観戦
小学5年生ころに相撲を見に行って以来、長い間好きなもののひとつだった。東京場所は少なくとも1日は国技館に足をはこび、その日以外はテレビで観戦した。相撲好きが高じて、大相撲の解説にゲスト出演したこともあった。玉錦や千代の富士のファンだった。

両国の国技館にて(平成2年、個人蔵)
マラソン観戦
マラソンもよくテレビで観戦した。「苦しさに堪えながら自己と闘っている姿に人間の生き方そのものを見る思い」がした。好レースは録画して、家族が外出中に、酒を飲みながら一人で観戦するのをひそかな楽しみとしていた。



あえて「私の好きな……」ものとはなにかと考えてみると、旅かもしれぬ、と思う。寄席通い、観劇、ボクシング観戦のような熱をおびたものではむろんなく、なんとなく気分がなごみ、悪くはないな、と思う程度である。(略)ただし、私には観光を楽しむ気持は一切なく、名所旧蹟、風光等には関心がない。旅と言えば小説を書くための調査旅行なので、図書館に行ったり人に会ったりするだけである。
楽しみは、夜、旅先の小料理屋に入ってその地に産する食物を肴に酒を飲むことである。
(「悪い癖」『私の好きな悪い癖』平成12年 講談社)
※ 所蔵の記載のない写真は津村節子氏蔵