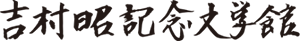- 掲載日2025年7月18日
-

概要
本年は、太平洋戦争の終結から80年になります。また、荒川区では、平成7年、戦争の惨禍を繰り返すことなく平和の尊さを広く伝えていくめ、荒川区平和都市宣言を行いました。この宣言から30年の節目になります。
18歳で、終戦を迎えた吉村昭は、敗戦を機に一変した日本人の態度や意識に違和感を持ち続けていました。自身が見た戦争は何だったのかを問い、また、戦争を通して人間の本質を探るべく、徹底した取材と調査を行い、昭和41年9月、「戦艦武蔵」(「新潮」新潮社)を発表しました。以降、戦争体験者の証言を全国各地に求め、文献資料と照合し、戦史小説を執筆しました。
今回の展示では、吉村の戦史小説から9作品を取り上げ、それらの取材ノートを中心に紹介します。また、吉村の妻で、小説家の津村節子氏特別インタビュー(約3分、制作:吉村司氏)を常時放映します。さらに、荒川区で、空襲を体験された方々の作品を含む空襲体験画「描かれた東京大空襲」(複製 すみだ郷土文化資料館蔵)を展示します。
吉村が、戦争体験者の貴重な証言を記録したノートからは、戦争の実態とともに、多くの亡くなられた方々の存在や、戦中・戦後を生き抜いた方々の計り知れない思いが伝わってきます。戦争の惨禍を繰り返さないために、戦争の記憶や記録を受け継ぎ、伝え続けることの重要性と、平和の大切さについて、改めて、考える機会としていただければ幸いです。
9作品を取り上げ、戦争体験者の貴重な肉声が記録された取材ノートを展示(一部、パネル展示)
<取り上げる作品>
・『戦艦武蔵』(昭和41年 新潮社)
・『殉国』(昭和42年 筑摩書房)(後改題「殉国 陸軍二等兵比嘉真一」)
・『大本営が震えた日』(昭和43年 新潮社)
・『細菌』(昭和45年 講談社)(後改題「蚤と爆弾」)
・『背中の勲章』(昭和46年 新潮社)
・短篇「手首の記憶」(『総員起シ』所収 昭和47年 文藝春秋)
・短篇「烏の浜」(『総員起シ』所収 昭和47年 文藝春秋)
・『深海の使者』(昭和48年 文藝春秋)
・中篇「他人の城」(『脱出』所収 昭和57年 新潮社)
津村節子氏特別インタビュー(約3分)を常時放映 制作:吉村司氏(吉村昭氏・津村節子氏ご夫婦ご長男)
吉村昭の発案で、戦中の体験を忘れないため、吉村家では毎年、終戦の日に、戦後の食糧難で常食としていた「すいとん」を食べました。この吉村家の恒例行事にまつわるエピソードを、お話しいただきました。インタビュー映像は、ご長男の吉村司氏に制作いただきました(令和7年7月収録)。
空襲体験画(複製 すみだ郷土文化資料館蔵)の展示
荒川区で空襲を体験された方の作品を含む、すみだ郷土文化資料館所蔵の空襲体験画「描かれた東京大空襲」(複製)を、吉村昭記念文学館エントランスで展示します。
主な展示資料
*は津村節子氏寄託資料
1章 戦争体験者の肉声を記録する
・「戦艦武蔵」に関する取材ノート* <戦艦「武蔵」>
・「殉国」に関する取材ノート* <沖縄戦>
・「大本営が震えた日」に関する取材ノート*<開戦前夜>
・「細菌」に関する取材ノートより、一部*(パネル展示)<細菌戦兵器>
・「背中の勲章」に関する取材ノート* <捕虜>
・短篇「烏の浜」に関する取材ノート*(パネル展示)<輸送船「小笠原丸」>
・「深海の使者」に関する取材ノート*<潜水艦>
・中編「他人の城」に関する取材ノート*(パネル展示)<沖縄戦・学童疎開船「対馬丸」>
・取材で使用したレコーダー*
・証言を録音したカセットテープ(一部)*
2章 戦争体験者に会い、小説を書くということ>
・短篇「手首の記憶」に関する取材ノート*<戦中・戦後を生きる>
・自筆原稿(草稿)「飛行機雲」(複製)*
・「特集/考える足」(「ダイヤモンド・ボックス」昭和57年5月、ダイヤモンド・ボックス社)*
3章 吉村が見つめた戦争―「人間の持つ驚くほどの順応性」―
・「吉村昭 加賀乙彦対談「戦争が日常だった時代」」(「波」平成3年9月号、新潮社)*
・「吉村昭 饗庭孝男対談「五十年たって見えてきた戦後」」(「波」平成7年6月号、新潮社)* など
<映像>
津村節子氏特別インタビュー「吉村家のすいとんを語る」(約3分)制作:吉村司氏(吉村昭氏・津村節子氏ご夫婦ご長男)
<空襲体験画(複製>
「描かれた東京大空襲」(複製)すみだ郷土文化資料館蔵
会期
令和7年7月18日(金曜)~9月17日(水)
※ただし、8月21日(木)、9月5日(金)は休館。
時間
午前9時~午後8時30分
場所
吉村昭記念文学館 2階 著作閲覧コーナー、エントランス